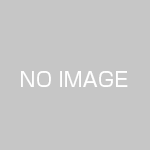中小企業大学校東京校、ブランディング支援3日間コース無事終了!
受講生にも事例企業、事例支援機関職員にも恵まれ、未だかつてないレベルの高い充実度の高い講義ができました。
川崎市の日崎工業株式会社の三瓶社長、川崎市役所のスーパー公務員、木村様にSDGs、カーボンニュートラル、環境経営を学び、
今年から初登場の埼玉県の南河原商工会の佐野経営指導員によるスリッパブランディングでの熱血さに感激し、
茨城県笠間市の有限会社鍋屋本展の小田部社長から地域事業者のブランディング事例発表から、同社の各事業の分析、提案をグループワーク、
合間におまけでワタクシがブランディング、戦略の構造と考え方、情報の効果的発信、強みの言語化、発想力の幅を広げるなど講義と小ワークで受講者の気持ちをつなぎ参加意識の高い講義でつなぎました。
主役はもちろん受講者です。
今回は、1日目から異変を感じてました。
レベルが高い!
いつもより平均年齢が10歳くらい高いのでグループでの話も盛り上がる。
話す内容に対しての理解度、顔色、うなづきが多い。しかも元気な人多し!声の大きい人も。
ここで、賭けに出た。
講義しながら内容のレベル上げて、構成を少し変えていく。
基本的な流れは同じですが、伝え方とロジカル部分を認識させながらも、予定したワークを少し変えていきました。
現場感や実際の地域の特色ある商品や取り組みをそれぞれの受講者が語る場を作り、班員のコミュニケーションもとるようにしました。
3日間、席順を変えてフレッシュな気持ちでいてもらいました。
(事務局さん大変ですがありがとうございました。)
これは、最近仙台校や東京校の他の講義でも行いますが、毎日同じだと閉塞感が漂う。自分のポジション作って黙る人もいる。人任せになったり役割が固定化することを防止できるので効果あります。いろんな人と交流する方がいいはずですし、今回はいませんでしたが(最近はあまり見かけないですね。バカンス受講者)困ったちゃんがいても1日なら我慢できるはず。
よって幻のワークも2件ありました。
今回用に作ったんですが、今後どこかで披露しますね。
2日目には、翌日の事例事業者の調査をネットにより各班行っていただき、仮説をたてること、顧客目線で強みや商品の魅力を感じること、情報発信力の分析などを行なっていただきました。用意したワークよりずっと実践的でどの班もしっかり動いてました。
そこでも、各班対抗で強みの付箋数を競っていただきました。なんと70枚もの枚数で各班やる気を見せてくださいました。いいね。このやるぞという気持ちに満ちた空間。今までの大学校講義でも最高レベルの充実度。
最終日の事例事業も鍋屋、小田部社長からの恐るべき発想と行動力、さらに哲学のような考え方生き方を聞いて感動した方も多かったと思います。
私がかつてお手伝いささていただいた事業者ですが、こういう素晴らしい方とお会いできるのも支援の醍醐味だとお伝えするのも私の裏メッセージでした。
その鍋屋さんの生きた事例を、もとに各班提案ワークしました。
例年2事業者の発表だったんですが、今年は1社をしっかり考えてもらうことにしました。これも賭け。
前日に強みを中心にリサーチしていたのでSWOTがスムーズでした。
よくあるグループワークの最初の変な沈黙の30分がなかった。あれ無駄よね。誰が口火を切るのか、どうやって進めるのか、あの手探りを無くしました。
さらに工夫したのは、各班の中小企業診断士、実力派経営指導員、モチベーション高い職員など1名ずつ前に出てもらって、約3時間のワーク時間で行うこと、タイムスケジュールを考えてもらいホワイトボードに記載して行く様を全員に見ていただきました。
強み再確認、
コンセプト、ドメイン
問題、課題
提案
それらを時間割していくと、時間が足りないことに気づく。前に出た受講者からこれは大変と言っていることを聞かせる。鍋屋さんは米屋、だんご、おにぎり、カフェ、栗、芋、チョコ、ネット販売など商品や店舗がたくさんで各班2つの事業を受け持っているので(これも選択制にして事前でグループ討議させるのも斬新でしたね。)、5人でこれを行うには、手分けして担当させることになる。必然的にのんびり黙ってるわけにはいかない。
ほぼ全員が動くワーク。おお!すごい光景だ。
やはり進捗悪い班も出てくるので、近隣の班に連れていき参考にさせること(隠密行動、とにかく盗め作戦)や、
AIもふんだんに使ってAI臭さをなくせばオッケー(具体的中身のないかっこいい言葉NG)でとにかくホワイトボード埋めていこうぜと私もアイデアヒント出しまくりで手伝いました。
いい人から盗めは鉄則。私も後ろでサボらず受講生目線で参加して(一応)プロ目線での応援しました。
スキルある人があまりズケズケ話すのもどうかと気を使うのが今回なかった。ミッションと時間を示せば、そういうこともなくなり協力しましたね。
この研修には、中小企業診断士養成課程関わった方々も数人いて、かつてさんじんここ東京校で行ったホワイトボードに書く戦略的なグループワークを思い出したかのようによい動きをしていただきました。ちゃんとわかりやすく班員に説明して置いていかずに役割分担とここぞという時に意見を言う職員さん、停滞していたがマインドマップを使うなど窮地を乗り切る職員さんなどさすがだな。そして成長したなと嬉しく感じました。
彼らが人を育てていけばいい。
役割を忘れてはいけない。
スキルを錆び付かせてはいけない。
よく考えたら10年前20年前より恐ろしくレベル上がってんじゃん。
支援機関はすごいです。やっぱり。
この研修の初日に講義のレベルあげます宣言した時にこういうことを言いました。
日常の支援業務でスキルと支援、意識レベルを低い方にあわせがちだけど、本来は標準化するなら高いレベルに合わせていくべき。それが発達支援計画そして小規模支援法などのあるべき姿。支援機関の生き残る方法。
この言葉が刺さったという受講者がいらっしゃったようです。
研修は受講者がつくるもの。
おかげさまです。よい研修ができました。皆様ありがとうございました。
あ、連日の夜遅くまでの懇親会もね。
大学のサークルか!?笑
みんなタフですね。タフさも大事。
鳴り止まないカーテンコールの拍手をいただいたような高揚感で東大和市を後にしました。東京校はまた来月と再来月も!
Facebook投稿より